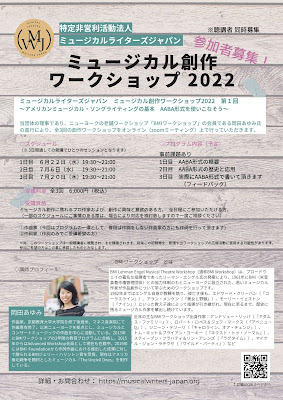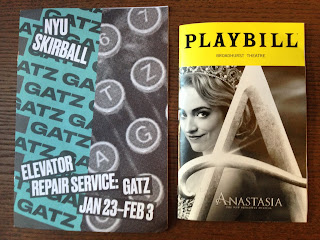この数日思いがけず家のインターネットがダウンしてしまい、投稿に間が開いてしまいました(汗)今日から続きを書いていきたいと思います。
____________________________________
これまでの回で、ミュージカルにおける歌と台詞の役割(第二回「なぜ歌うか」)、ミュージカル・ソングにおける歌詞と音楽の役割(第三回「サブテキスト」)について見てきました。
今回はミュージカル・ソングについての最終回として、歌の持つ効果という視点から、「歌の作り」について書いていきたいと思います。
ミュージカルではそれぞれの曲は基本的には作中で一度しか聴かれないため
[1]、その条件の中で歌という表現の効果が最大限発揮されるよう、「歌の作り」として以下のようなことが意識されています。
メロディー:歌いやすく、かつ歌詞が聞き取りやすいか
歌詞:論点は1つに絞られていて、かつそれが論理的に展開しているか
音楽:特定の音楽ジャンルに寄りかかっていないか
形式:AABA形式で書かれているか
その他:Cliché(クリシェ:決まり文句)を無意識に使っていないか
メロディーについては、具体的には言葉のアクセントが正しく反映されているか、自然な英語のリズムで喋ったように聞こえるか、適度に正しく"Rhyme"(ライム:韻律)を踏んでいるか、そして言葉数が多すぎたり少なすぎたりしないか等が、メロディー自体の魅力もさることながら、良い歌の必要条件とされています。
歌詞の論点は"Hook"(フック)という、歌詞(及びメロディー)の1フレーズに凝縮させます。このフックは曲中何度も繰り返され、大抵の場合、曲のタイトルにもなっているのですが(例:『ウェスト・サイド・ストーリー』"Maria"「マリア」)、これは論文でいうところの結論にあたり、歌詞の全ての内容がこのフックに向かって収束していくように論理を組み立てます。このような組み立ては、ミュージカル・ソングが曲の進行に沿ってその内容がスムーズに理解される必要がある為で、観客をつまづかせてしまうような論理的矛盾や、「考えれば理解できる」ような少しの論理的飛躍もないように展開することを目指します。
形式については、近年のミュージカル・ソングの多くがポップス曲の「ヴァース‐コーラス形式」でも書かれていますが、物語や概念を伝えるには、本来このAABA形式(各セクションが8小節ずつの計32小節で1コーラスを構成する歌の形式)が最適とされており、多くの名曲もこの形式で書かれています(例:『ウェスト・サイド・ストーリー』”Tonight”「トゥナイト」)。
特定の音楽ジャンルを用いると、その途端に音楽が一般化してしまい、キャラクターという個人の、固有の感情から距離ができてしまって、観客が真剣に感情移入することができなくなるとされています。作品全体が特定の時代や音楽ジャンルに属するような場合でない限りは、できるだけ特定の音楽ジャンルに寄りかかることは避け、キャラクター自身から自然と現れて来る音楽を模索します。
ここで言うCliché(クリシェ:決まり文句)とは、歌詞における常套句もさることながら、音楽的に使い尽くされた決まり文句(特定のコード進行や、特定の音程を多用した伴奏形等)のことも指し、上記の、特定の音楽ジャンルを用いない事と同じ理由から避けるようにします。
ここまで、歌の効果をより発揮するという視点で見てきましたが、言葉には歌う事によってその意味が増幅されるという側面もあり、そのため歌詞における言葉の選び方や内容によっては、必ずしも意図しないネガティブな効果が生まれてしまうことがあります。そのため以下のことも意識されています。
歌詞:禁句を使っていないか、内容が自己憐憫になっていないか
禁句を歌詞の中で表現として絶対に使ってはいけないわけではないのですが、その意味が増幅される事を念頭に置き、特別の意図がある場合(キャラクターの口癖であるとか、特に衝撃的な効果を出したい場合など)に限ってよほど慎重に使うべきとされています。また、コメディーとして笑い飛ばすのでない限りは、キャラクターが自己憐憫の内容を歌うと、観客が自身のコンプレックス等とリンクさせて捉えてしまう可能性があるため、こちらも避けるべきとされています。
以上、箇条書きになってしまいましたが、歌のポジティブな効果を最大限に発揮させ、ネガティブな効果を最小限におさえる為に意図された歌の作りを見てきました。ソング・ライティングの際にはこれらを意識して取り組むのですが、互いに密接に絡み合う要素も多く、初稿からこれらを全てクリアするのはなかなか難しいです。実際にはまずはともかくベストだと思う状態に書き上げて、人に聴いてもらっては指摘を受け、書き直しを重ねる事で仕上げて行く、という行程を辿ることが多く、BMIワークショップでもその活動を重ねています。
以上、三回を通して駆け足ながらミュージカル・ソング、及びそのライティングについて、特に重要であると感じている事をまとめてみました。次回からはBMIワークショップについて書かせて頂きます。
*追記:2025年8月3日に続編、「
第九回:日本からBMIワークショップを目指す方へ」を投稿しました。ご興味持って頂けた方はぜひこちらもご覧ください。
**********
[1] “Reprise”(リプライズ)として、作品にとって特に重要な曲などが作品の後半で再び歌われることはあります。